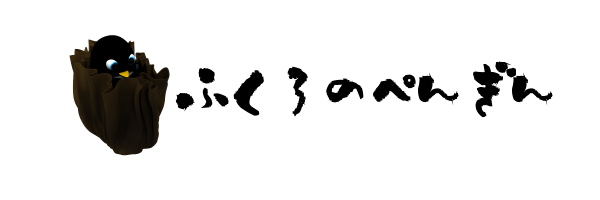「昨日今日の話じゃないなあ」
目の前の外科医はモニターをみながら呟いた。
六畳間ほどの広さの診察室は、割り当てられたその役割の重さも相まって実際の狭さ以上の息苦しさを感じさせた。
机上のモニターには検査結果の数字とともに、心エコーの動画が再生されている。
拍動する心臓が全身に送り出すはずの血液は、モノクロの画像の中で青と赤に塗り分けられて渦を巻くように戯れていた。
「・・・かなり進んでるな・・・」
再び呟いた外科医のそれは、それでも患者である私に向けられた言葉というよりは独り言のように感じられた。語尾が「ね」ではなく「な」であることもそれを表していた。
口数の少ない執刀医
時は下り、すでに手術を終え退院してから一週間後、術後初めての外来受診を終えたときのこと、病院から自宅へ戻ると、老齢の母はいつものようにベッドで横になり、ipadを操作していた。
テレビからはアマゾンプライムの韓国ドラマが流れている。韓国語を理解していないはずの彼女は画面を一瞥もせずipadをさわっている。ドラマの内容には興味が無いらしい。画面を見ないのなら吹き替えにすればよいではないかと意見したことがあるが、日本語だと気になるから、と意味の分からない答えが返ってきたことがある。
「どうだった?」
コロナ禍の始まってまもなくの頃である。帰宅すぐに手を洗いに向かう私の背中に母が話しかけた。私の体の状態、直前の診察結果を問うた質問だったのであろうが、私はつい、いつも思っていたことが口をついて出た。
「あの先生、ホントに喋んないわ」
的外れであったはずの返答である。しかし一拍の間のあと、どこかツボをつかれたように母は盛大に笑った。
そんなにおかしなことを言ったつもりもない。不思議に思いつつ手を洗って居間に戻ると、母はまた韓流ドラマをBGMにipadをさわっていたので先程の笑いの理由は聞かなかった。
その理由が分かったのはそれから1ヶ月後、2度目の受診の後のことだった。
「今日も喋らなかった?」
帰宅早々に母がした質問である。
私の主治医があまり喋らないという事は、前述した、たった一往復だけの会話以外にしたことはないはずである。
しかし母ははっきりとその事を覚えていた。
質問に違和感を感じながらもやはりその日も手を洗って戻ると母は続けた。
「看護婦さんに言われた」
それは手術当日のことらしい。家族待合室で手術が終わるのを待っていた母は、いよいよ手術が終わる頃、看護師に話かけられた。
「先生、殆ど喋らないですけど、気にしないで下さい」
場違いな言葉である。生死に関わるかもしれない、少なくとも一度心臓を止めて行う手術を待つ患者の家族にかける言葉ではない。それでもその看護師は、その台詞をこのときに発するべき言葉としてそれを選んだのである。それほどまでにこの医者は喋らないのであろう。
おそらくはこれまでに家族から苦情めいた話があったのかもしれない。苦情までいかずとも、看護師達は接する家族の表情からその不安や不満の感情を感じ取っていたのかもしれない。
また、それ以上に毎日職務としてその医師に接する中で、看護師たち自身がそう思っていたからこそ母にそう言ったのではなかろうか。
看護師のその言葉通り、その執刀医は手術室から出て長椅子に腰掛けると、昼時のそば屋でサラリーマンがおしぼりで拭くかのように手で顔を覆って大きく息をした。全身のエネルギーを使い果たしたように、その後もしばらく両手を頬に当てたまま正面を向いて止まっていた。やはり看護師の言ったように何も喋らなかった。
ただその姿に、母はその執刀医が全力で治療に当たってくれたことを確信して安心するとともに感謝の気持を強くしたらしい。
いずれにせよ、私の主治医はその技術力はともあれ病院のスタッフも認める口数の少ない医師だということがこの時点でハッキリとしたのであった。
しかし、そのことは治療をすすめる中で分かってきたことである。この日初めて心臓外科を訪れた私は、この無口な主治医にどう応じてよいのか困惑していた。
おかしな文体
ここまで読んでいて読書慣れしている方ならば特に、過去3回分の記事と文章の雰囲気が違うことを感じていることであろう。妙に文学調である。小説のような文体である。
影響されているのだ。
つい先日、良質のスポーツノンフィクションを読了した。
名古屋のプロ野球球団中日ドラゴンズを黄金時代に導いた落合博満監督を描いた名著「嫌われた監督」を読み終えた直後なのだ。
文章が引きづられているのだ。
任侠映画を見終わった昭和のオヤジどもが、肩を揺らしながらシネマを出ていくように。
この妙な空気感が、秋の訪れとともに乾いた空気を呼び込もうと、すべての窓を開放しているにも関わらず出ていかないのだ。
しかもその件について、わざわざ1チャプターを費やして説明する始末である。
きっと、心臓弁膜症の体験談を求めて少ない検索結果の中から偶然にもこの記事を見つけ出した読者の方は、戸惑い、あるいは憤慨しているかもしれない。
でも止められないのだ。そういうものなのだ。
いったい私は何を言ってるんでしょうか?
ただし、この文章、書いていてしんどいのである。
本来のスタイルではないのでしんどいのである。
だから徐々に、もしくは突然に元にもどっていくことでしょう。
しばし我慢して読み進めて下さい。
手術の予定
無口なその主治医はモニターに映し出される心臓のエコー画像にボールペンの先を向けた。
「この辺全部戻っちゃってる」
血液が逆流しているという意味のようだ。最低限の説明であるが、素人の私が見ても一度通り抜けたはずのその流れが不自然に戻って乱流を作っているのは確認できた。
医師は一枚の書類を机の上の彼と私のちょうど中程に置いた。
「弁膜症手術説明書」
一番上にそう書かれた書類に時折簡単な書き込みをしながら彼は説明を続けた。

説明とは言うが、その書類に書かれた選択肢に丸をつけながら、ただそれを読んでいるだけである。それでも、ただ表層の事実を伝えるためならばそれで十分だ。なにしろ当の患者本人も自分に何が起こっているのかをハッキリと認識していないのだから、事細かい説明をされるよりもまずはざっくりとした状況説明が必要なのだ。
示された病名は「僧帽弁閉鎖不全症」
必要とされる手術は「僧帽弁形成術」
術式は「MICS」
心臓にある4つの弁の内の一つ、左心房と左心室の間にある「僧帽弁」が完全に閉じなくなっていて、そのため左心房から左心室へ送り出された血液が再び左心房へ戻ってきてしまっている。
そのためその僧帽弁を正常な状態に形成する(形を整える)手術を行うということ。
同時に、作られた血栓が血管を巡って脳梗塞などになるのを予防するために、左心耳と呼ばれる部分を切除するとのこと。その部分には最も血栓が溜まりやすいそうだ。
彼は説明しながら書類の中程にあった心臓のイラストにいくつか図を描いていった。
血液の流れ、通常よりも大きくなった左心室、僧帽弁の動き、そして左心室の上に何やらコブのようなものを描き足した。
このコブのようなものが左心耳と呼ばれるものらしい。これを切り取るということだ。
「これはね、3分位で終わる」
聞き間違えたのかと思った。僧帽弁形成術のついでに行う左心耳切除は3分で終わる。たしかにそう聞こえた。
あとで調べて分かったことだが、心臓の左心耳という部位は胎児の頃に機能していて、生まれた後は必要がなくなった、いわば廃用部品らしい。盲腸みたいなものか。
それにしたって心臓の一部である。切り取って処置をするのに3分というのは本当なのか。聞き直そうかと逡巡しているうちに説明は淡々と進んでいく。
手術はMICS(ミックス)とよばれる低侵襲手術で行う予定らしい。
MICS ー Minimally(最小限の) Invasive(侵襲的) Cardiac(心臓の) Surgery(手術)
胸の正面、肋骨の中央から切り開いて手術を行う胸骨正中切開ではなく、脇の下から乳首の辺りの部分に数箇所の小さな穴を開けて行うもの。
肋骨のスキマから菜箸のような細長い器具を突っ込んで内視鏡下で行う。肋骨を切り開く場合に比べて手術時間も短く、また体にかかる負担も少ないため回復も早い方法。
手術時間は長くても3時間。普通に進めば2時間。入院期間は5日~1週間。
これも想像していたよりも随分とコンパクトな時間である。手術に4~5時間、入院に2~3週間をイメージしていたので多少拍子抜けした。その前の「左心耳切除に3分」の話もあり、今や心臓手術というのはそんなにカジュアルになっているのか、我々の想像よりもずっと簡単なのかと多少の安堵を感じた。
同時に、この人の言っていることを鵜呑みにしてもいいのかな?という疑問が生じていたことも確かであった。
0.5%
そんなとき、おそらく手術を受ける患者が最も気になる数字の話になった。
手術危険率、入院死亡率である。
つまり、この治療を行う場合に死んでしまう可能性である。
「1%~2%、どうしても絶対って言うことはないからね」
この数字は事前に知っていた。
弁膜症の診断が出て以来その病気についての情報は収集しまくっている。ほとんどWEB上の玉石混交の情報ではあるが。ただ、患者数は国内だけでも300万人はいると言われるが、ガンなどと比べると未だあまり大々的には語られていない病気である。それ故に有象無象の怪しげな情報もあまり見当たらず、そのほとんどが実際にその病気の治療・研究に携わっているものからのものであった。ざっと見渡してみても情報のブレはほとんどなく、どのサイトでも同じような内容が語られていた。
そこで目にした数字はやはり主治医が言ったものと同じであった。
「もうちょっと低いかな」
彼はしばらく考えた後、「%」の文字の前に「0.5」と書いた。
入院死亡率0.5%
おそらく1~2%というのは全体の数字なのだろう。その中には80代を超えたお年寄りもいれば20代の若者もいるだろう。弁膜症以外の病気を持っている人もいるだろう。体力の違いもあるだろう。全部ひっくるめての1~2%である。
私は50を少し超えたばかり。年相応の劣化はあるが特に大きな病気も抱えていない。いや、その大きな病気を治しに来ているのではあるが、問題はそこだけである。体力も十分だ。
おそらく主治医はそこを判断して数字を下げたのではないか。
入院死亡率の項目のすぐ下には、入院日と手術日を記入する欄があった。
「7月下旬に出来るけど」
話がものすごい勢いで進んでいる。前回の記事でも書いたが今までこの病院で診察を受ける過程において、それでは手術をしましょうという結論に至る話をしたことは一度もない。それでも手術前提で話は進んでいる。
それにはここに至るまで患者の私自身がそれに対しての疑問を表に出していないことに加えて、おそらく重症であろうこの症状において、経過観察などという生ぬるい選択肢は考えられないということもあるのであろう。
実は専門医の循環器内科、心臓外科においてはハッキリと言われなかったことを、この病気を発見するきっかけとなった脳神経内科の医師には循環器内科の次の診察時に言われていた。
「手術しないと多分長生きはできないよ」
そういうことなのであろう。その脳神経内科の医師は対照的にフランクでよく喋る人であったというのも面白いものである。
コロナと手術
一つ確認したいことがあったので、淡々と、ベルトコンベアに載せられた製品のように進んでいく話の流れをせき止めて、私は質問をした。
地元の自治体が基礎疾患を持つ人のコロナワクチン接種の募集を始めている。ワクチン接種は手術の前に済ませておいたほうが良いのだろうかと。
この質問の答えも実に簡潔、言葉は最低限だった。
「ん、そうね」
肯定の意味であると解釈して、主治医の言葉の少なさを補うように私自身が話を進めた。
「受付が来週から始まります。その次の週から接種が受けられるようになるので、2回目の接種の時期を考えればもう少し後のほうが良いのですが」
この日は6月4日である。1度目のワクチン接種と2度めの間に3週間以上が必要、さらに十分な抗体ができるのに3週間と言われていたことから合わせて6週間、余裕を見て2ヶ月後はどうだろうかという提案である。
病院側からの打診ではなく、私からの提案である。
「その後だと、8月4日が空いてる」
「空いてる」という言葉が心臓、循環器の手術を待っている人がいかに多いかを物語っていた。
8月4日であればそれまでの工程をこなすには十分な期間がある。
「その日でお願いします」
結局ここに至るまで、手術をするのかしないのかという選択についての会話を一度もすることなく、手術の日程が決定した。
8月3日に入院、この日からちょうど2ヶ月後の8月4日、手術である。
その予定が決まると、寡黙な医師の口数はさらに少なくなった。
いや、とうとう言葉を発さなくなった。
もう退室してもよいのだろうか?
それでは外で待っていて下さいという指示もないが、勝手に出ていってよいのだろうか。この後どうするのだろうか。
思い悩んでいると医師は一枚の書類を差し出さして、署名を促した。手術の同意書かと思ったがそうではないようだ。
世はコロナ禍。やはり病院としても感染対策はきっちりと行わなければならない。そのため、入院患者には全員入院前のPCR検査を課していた。その入院前検査の同意書だった。

署名をすませると、再び狭い空間に沈黙が訪れた。淀んだ空気が息苦しい部屋をさらに居心地の悪いものへと変えていた。
気まずさに耐えきれなくなった私はとうとう席を立った。
「ではよろしくお願いします。ありがとうございました」
そう言って部屋を出た後、大きなため息をついた。それは手術が決まったことへの安堵なのか、自分の病気への落胆なのか、はたまた妙な空間から脱出できたことからの開放感であったのか。
それは今でもわからない。
部屋から出てベンチに腰を下ろした私は、事務員がこの後の予定を知らせに来るのを待つのであった。
そして、なんだかんだ言いながら、今回は最後までなんとなく小説調になっていたのに気がつくのである。
次回は止めよう。
疲れる。時間がかかる。